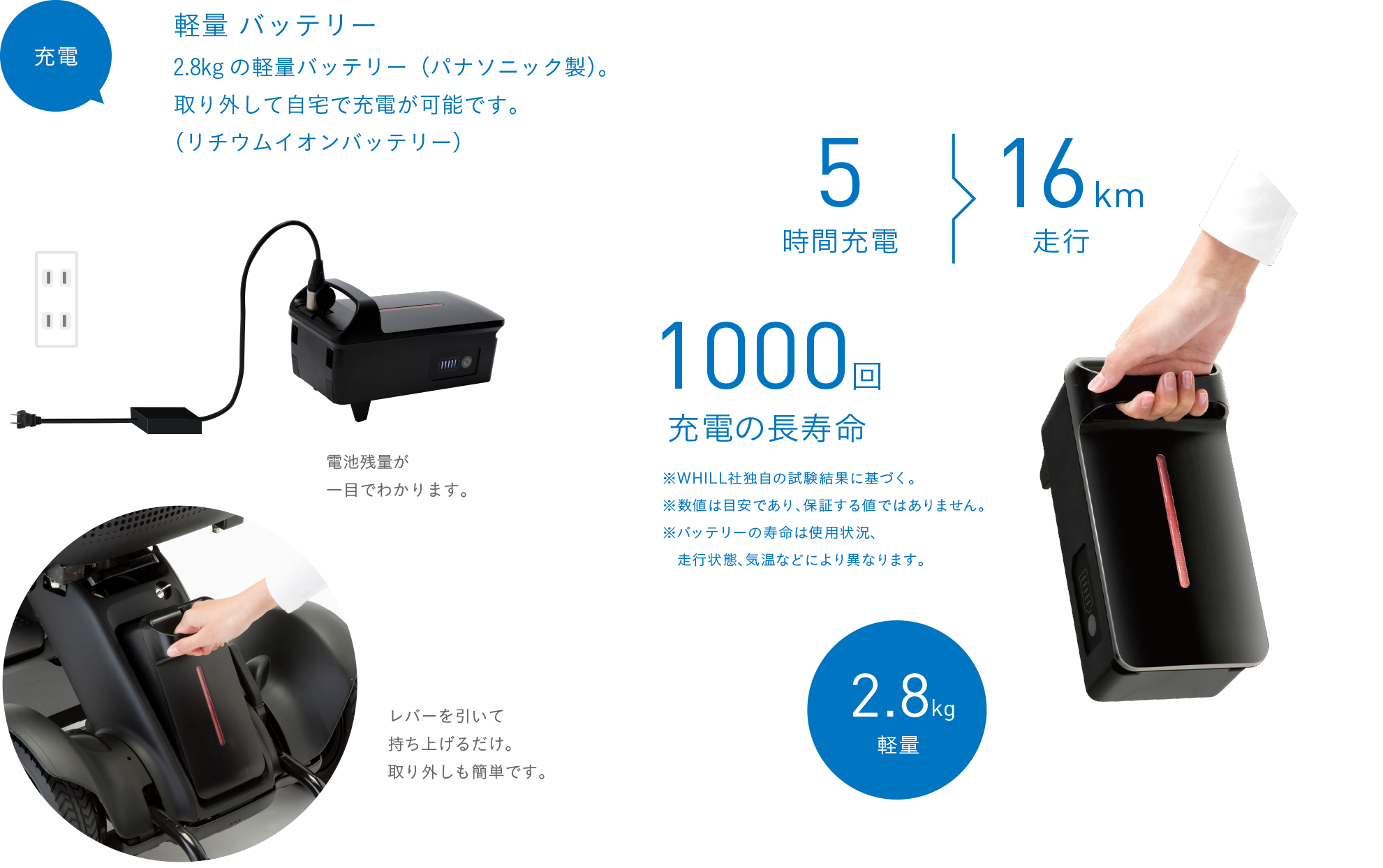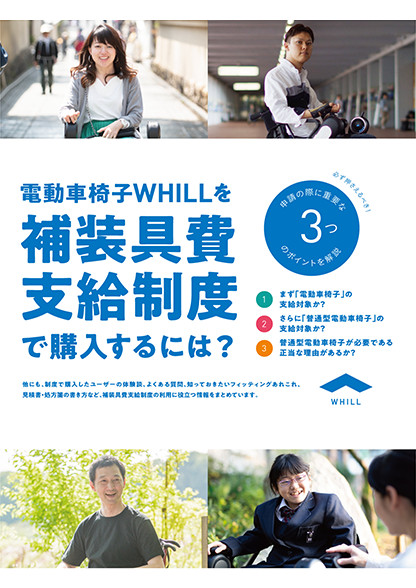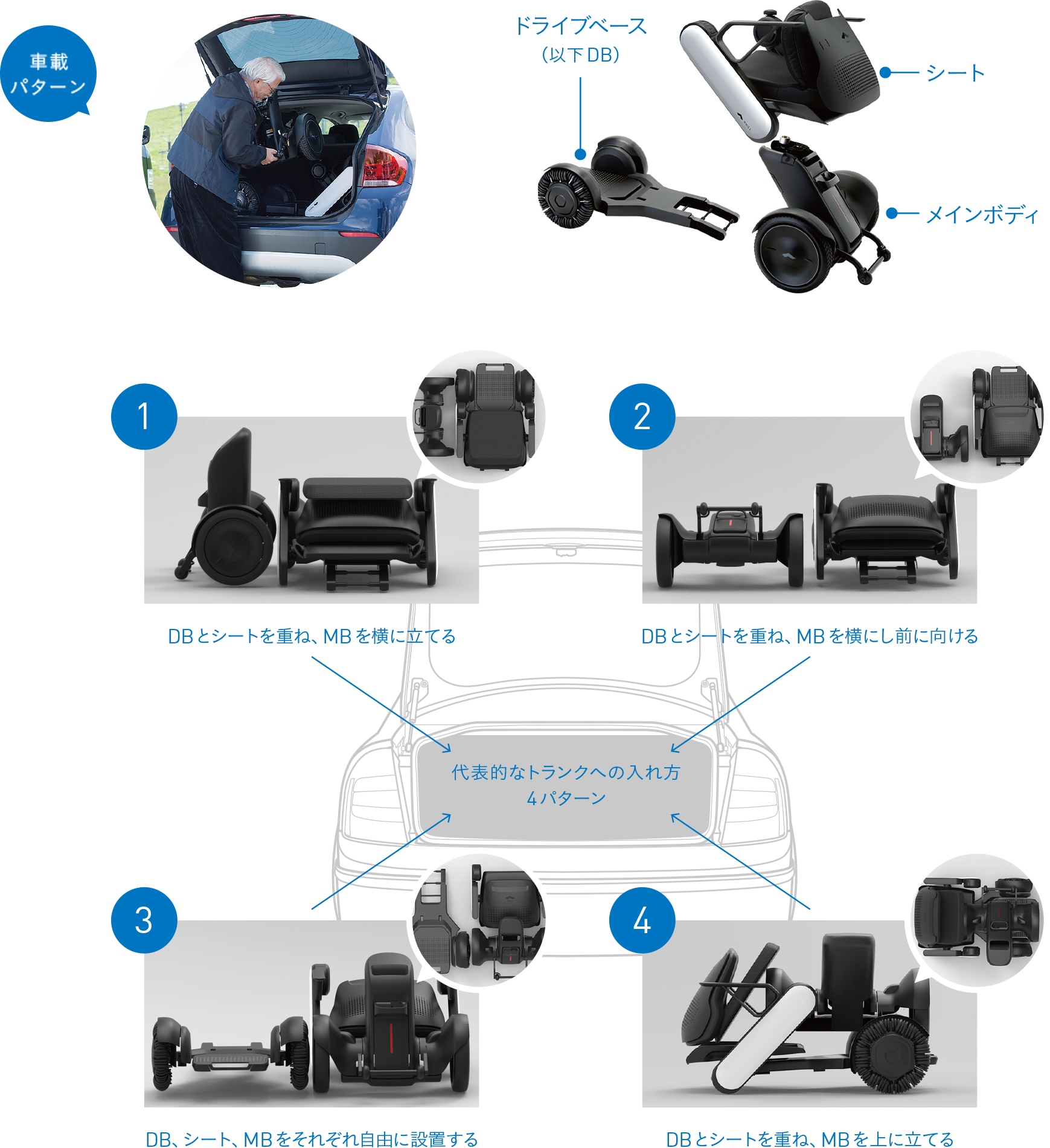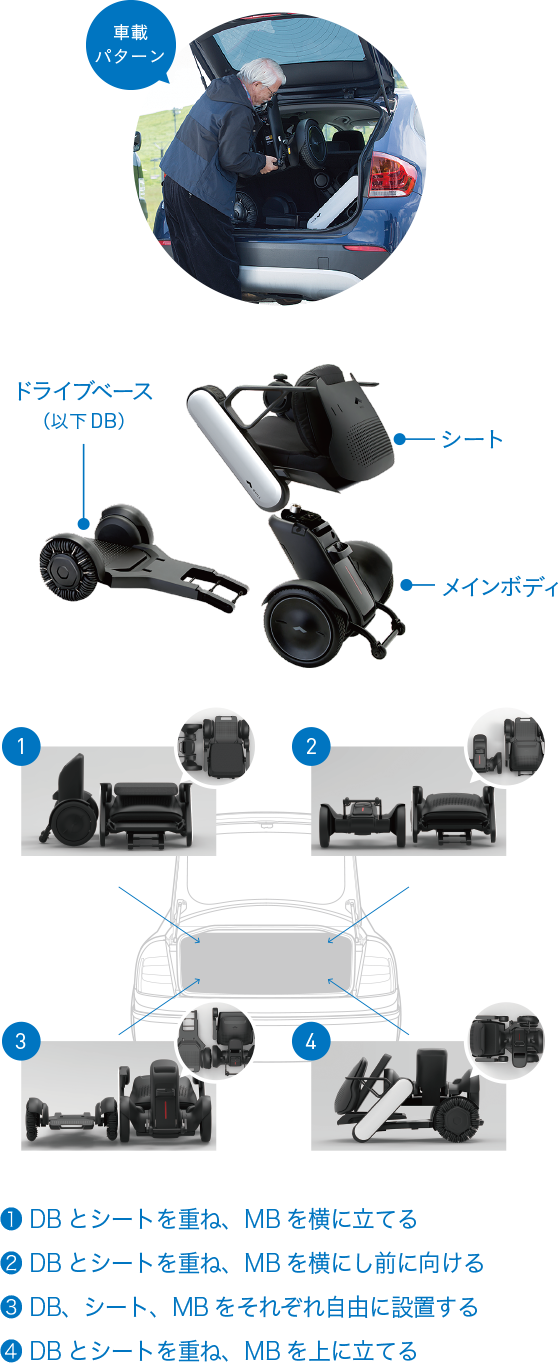電動車椅子が欲しいけど、費用がかかるし…とお悩みではありませんか? 「補装具費支給制度」を活用すれば、電動車椅子の購入に補助金が出るケースがあります。この記事では、制度の概要と申請の流れ、支給判定のポイントなどをご紹介します。制度を上手に使って、今の生活をよりよくする一歩を踏み出してみませんか?

補装具費支給制度とは何か?
補装具費支給制度とは、障害者が日常生活や就労・就学のために必要な、身体の失われてしまった機能を補完・代替する用具を購入・修理する費用を支給する制度です。
障害者の生活の向上や自立支援を目的としています。
平成18年10月施行の障害者自立支援法に基づく
「障害者自立支援法」とは、“障害者が地域生活や就労を通して自立すること”を支援するための法律でした。
これは、これまで障害の種別ごとに異なる法律に沿って行われてきた福祉サービスや医療を、ひとつの制度の下に行えるように整備したものです。
そこに提示されたのが「補装具費給付制度」です。現在は、”難病の患者”を対象として加えるなどの改正を行い、平成25年から新たに施行された「障害者総合支援法」に引き継がれています。
申請は各市区町村で行う
補装具費支給の申請は各市町村へ行います。
申請を受け付けたあと、市町村は、適切な補装具の判断、支給の判断を決めるための情報提供や相談、必要な調査などを行い、最終的に支給の有無や金額の判定を行います。
また、都道府県や国も支給の判定や障害者の生活支援が円滑に行われるよう、助言や情報の提供に努める責務があります。
補装具に該当するものには何があるか?

では、具体的に、支給対象となる補装具には一体どのようなものがあるでしょうか?
補装具とは、障害者が日常生活や就労・就学に用いるもので、長期にわたって使用されるものを指します。
例えば、義肢や姿勢などを保持するための装具、車椅子、視覚・聴覚障害のための補装具、重度障害者のための意思伝達装置など、障害に応じてさまざまなものがあります。
対象となる車椅子には電動車椅子もある
車椅子が補装具となる対象の障害は、下肢機能障害、体幹機能障害、平衡機能障害、心臓機能障害、呼吸器機能障害です。
そのうち、電動車椅子支給の対象者となるのは、歩行が困難で、さらに手動式車椅子を自分で走行させることが難しい場合です。坂や砂利道が多く、手動での車椅子駆動は負担が大きいなど、地理的環境による理由も含みます。
購入だけでなく、修理も該当する。耐用年数もチェック
先ほども述べたように、補装具とは長期にわたり使用されるものです。補装具の再支給や修理についても配慮されています。
厚生省の資料には、各補装具の耐用年数が示されていますが、使用者の身体状況や使用頻度により、実際の耐用年数と提示されている年数にはズレがあります。耐用年数が過ぎても修理して使用できるものには、その修理に対して支給があります。耐用年数が過ぎていなくても、新たに購入したほうが合理的な場合は、再支給の対象になります。
補装具費支給制度利用に必要な、申請書、意見書、手続き

実際には、どのような人が補装具費支給を申請できるのか、また申請の手順と補装具購入までの流れはどのようになっているのかなどについて見ていきましょう。
身体障害者手帳保有あるいは指定難病等の診断が出ていること
支給の対象者は、身体障害者手帳を所持していることが必要です。
また、身体障害者手帳の交付を受けていなくても、障害者総合支援法で定めている指定難病患者で、補装具が必要と判定される場合も支給対象になります。
補装具費支給制度申請書は、市区町村の障害福祉窓口へ
補装具費の支給申請を希望する場合、まずは役所で相談を行うための準備が必要です。
申請に必要な書類は、おおむね以下の3点です。各市町村の障害福祉窓口に提出します。
- 補装具費支給申請書(購入・修理)
- 補装具製作業者の発行した見積書
- 医師による補装具費支給制度意見書(必要な場合のみ)
必要書類は自治体によって異なり、指定フォーマットがあるケースや身元確認資料が必要なケースもあります。まずは各自治体のホームページで確認したり、窓口へ連絡するなどして、必要書類について確認してから、準備することをおすすめします。
そのため、「補装具費支給意見書」の作成を医師に依頼します。合わせて、補装具の製作業者への見積もり依頼も必要です。それらの情報が不足すると市町村も支給の判定が難しくなる事例があるようなので、申請前に各市町村に連絡をし、申請に必要な情報と流れについて確認したほうがよさそうです。(補装具によっては意見書が必要ない場合もあります)
補装具費支給制度意見書とは? その料金は?
医師に作成を依頼する「補装具費支給意見書」の役割は、支給判定のために必要な情報を医学的な立場から提供することです。補装具の必要性、処方内容、使用効果などについて、市町村の障害福祉担当が理解できるよう、詳しく記載してもらいましょう。料金は、他の診断書同様に有料で、病院ごとに異なります。
障害者福祉センターなどに出向いて、判定を受ける
さらに、電動車椅子に関しては、障害者福祉センターなどの「身体障害者更生相談所」とよばれる専門機関にて、支給の必要性を判断してもらう必要があります。そのほかのものは、補装具によって判定方法が異なるため、詳しくは市町村に問い合わせましょう。
補装具費支給券の交付を受ける
支給が決定したら、「補装具費支給決定通知書」と「補装具費支給券」を市町村から受け取ります。
その後、補装具業者に支給券を提示し、契約を結んで購入、という流れになります。
支払った費用を市町村に請求し、代金を受け取ります。手続きを踏めば、市町村が直接業者に代金を支払うこともできます。
(代理受理方式)。
補装具費支給の基準額、所得区分は?
基本的に、補装具を購入する費用の1割は利用者の負担となり、それ以外の9割は支給対象となります。
補装具費支給の、所得区分。46万円とは?
利用者負担額は、所得に応じて月額の上限が設定されています。また、住民税の所得割額が46万円以上の方がいる世帯の場合は、補装具費支給の対象外です。
逆に低所得(住民税非課税)の障害者については、利用者負担額が無料です。
電動車椅子購入が可能かの判定のポイントは?

電動車椅子を購入したい方は、補装具費支給制度が適応される条件を確認してみましょう。
1. まず、電動車椅子が必要かどうか?
介護保険制度など他の制度が適用されない場合で、身体障害者手帳を保有しており、上肢機能障害によって手動車椅子の走行が難しい方、呼吸機能障害、心臓機能障害によって歩行が難しい方など。また、障害者手帳を保有していなくても、指定難病により歩行が難しい方は、電動車椅子支給の対象になる可能性が高いようです。
2. 電動車椅子には二種類ある?
電動車椅子には、「簡易型」「普通型」の二種類の支給対象があります。
「簡易型」電動車椅子とは、手動車椅子に電動ユニットを取り付けた車椅子で、電動と手動の切り替えができます。
「普通型」電動車椅子とは、電動でのみ走行し、手動に切り替えることはできません。
平地で車椅子を漕ぐことができる場合、原則「簡易型」電動車椅子の支給になります。ただし、漕ぐことができたとしても、普通型電動車椅子を使用しないと自立した行動が難しい理由を説明することができれば、「普通型」電動車椅子の支給申請が可能になります。ウィルは「普通型」電動車椅子に属します。
3.大事なポイントは、補装具を使うことで自立できること
電動車椅子を補装具として支給してもらうことができた方の事例をあげると、
「就学前までは手動車椅子を使用していたが、大学の構内に急な坂道が多くあり、電動車椅子が必要になった。」
「肘の関節が動きにくいことで手動車椅子を漕ぐことが難しく、今までは母に車椅子を押してもらうなどして通学していたが、ひとりで安全に通学をするために電動車椅子を支給してもらった。」
「進行性の病気で、手動車椅子を長時間漕ぐ握力が弱くなってきたこと、少しの段差や坂道でも付き添いがいないと通勤が難しいという理由から、電動車椅子が支給された。」
など、日常生活において頻繁に利用する環境で、「補装具があることで、ひとりで行動することが容易になる」ということが大きなポイントのようです。
ウィルを補装具費支給制度で購入する際の注意点とは?
社会で自立した行動をしたい。補装具費支給制度は、そんな障害者の希望を支える制度です。支給決定までには、市町村、医師、更生相談所や業者、関係者が連携を組み、「その人にとって一番よい補装具は何か」を判定することを大切に考えて取り組んでいます。
ウィルの電動型車椅子が、あなたの「自立と社会参加」という希望を叶える補装具となりうるか。
ここで自己診断をしていただけます。
ウィルを補装具費支給制度で購入する際の詳しい情報については、こちら

これからの毎日が、より輝きにあふれたものになるかもしれません。