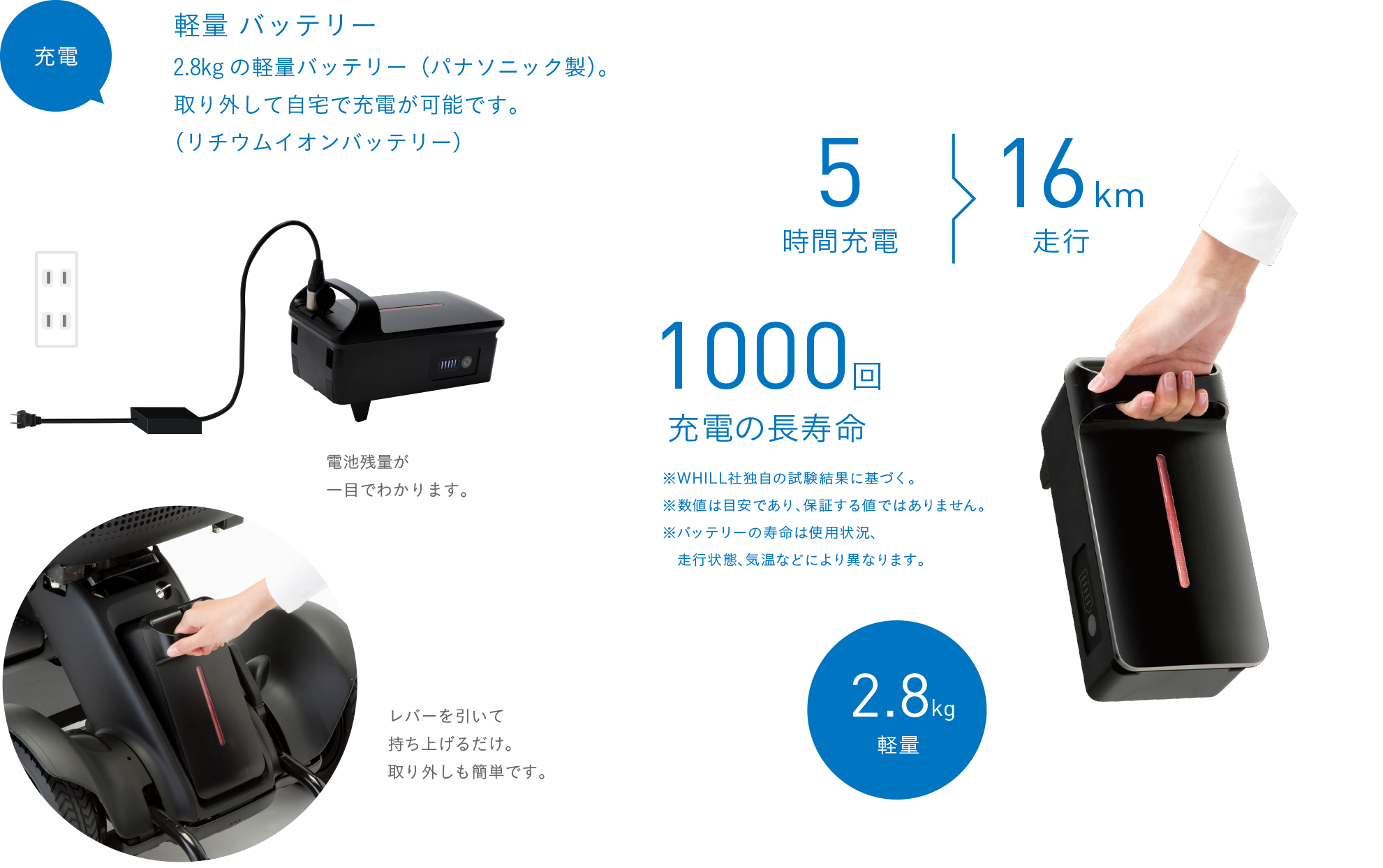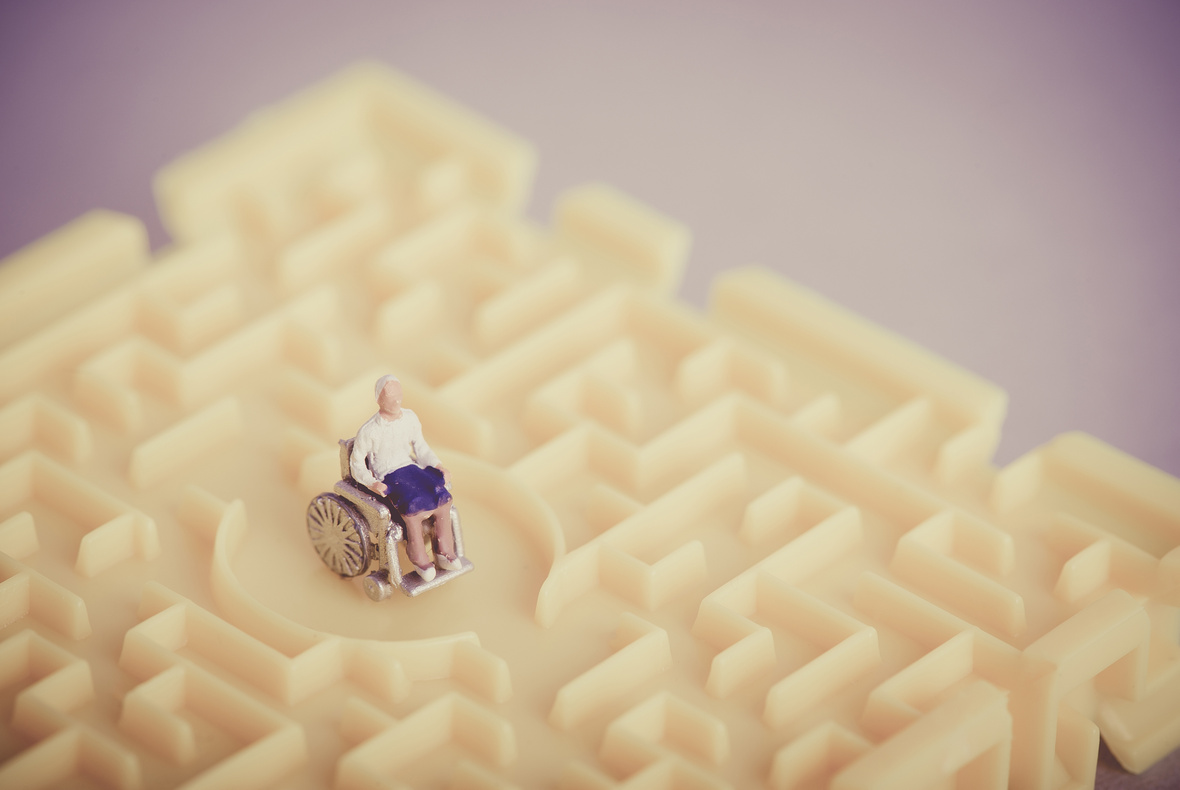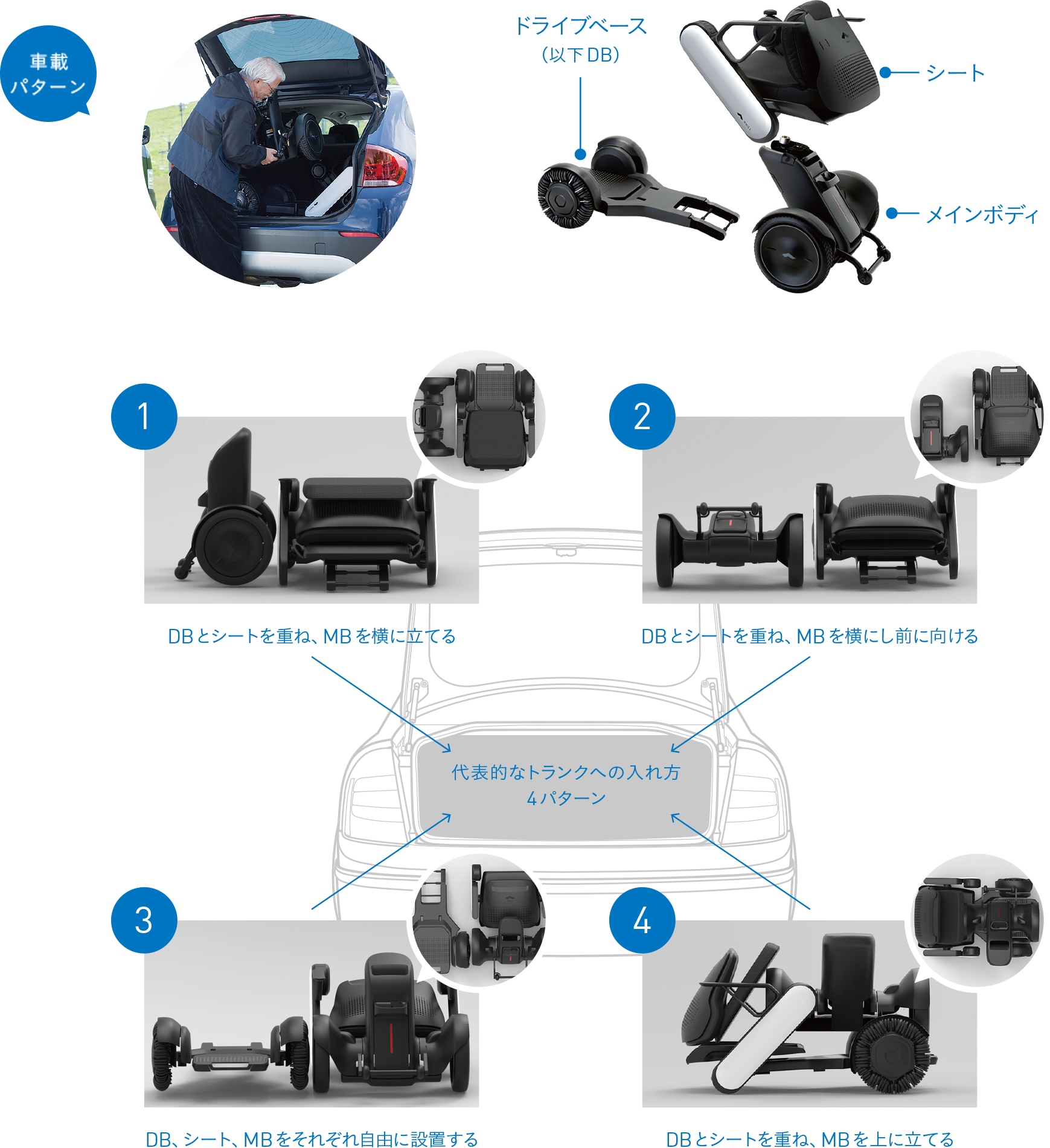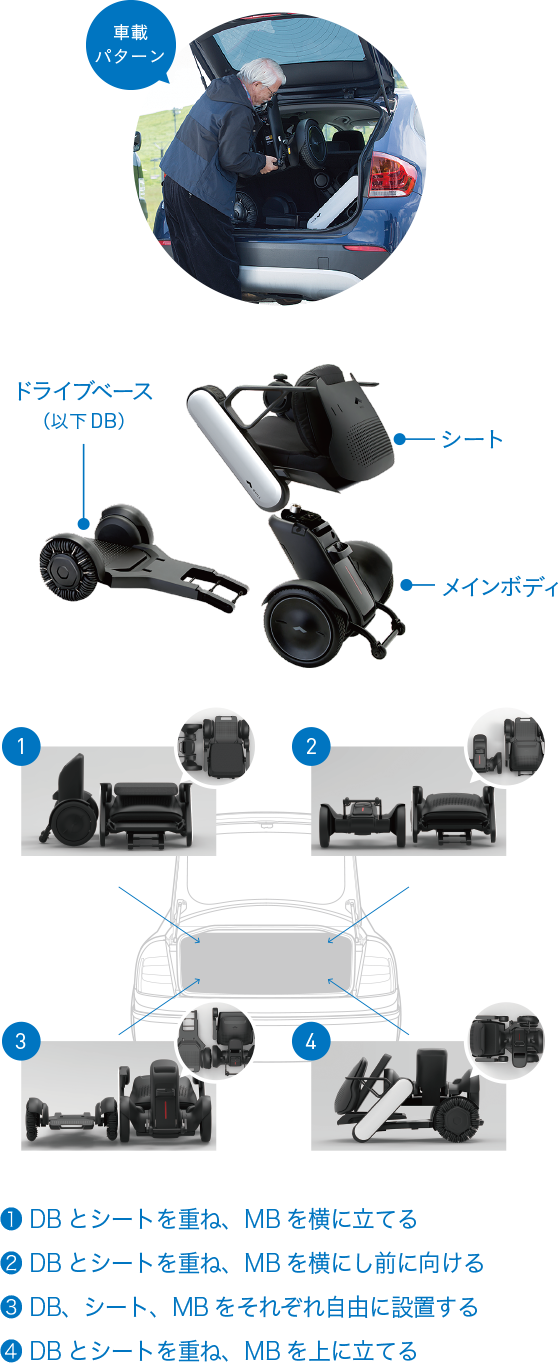バリアフリーという言葉の本当の意味をご存じですか? 世の中でスタンダードとなっているバリアフリーの意味と、ひとりひとりの中にあるバリアフリーの意味が等しいものになっているか、今一度確かめてみませんか?この記事では、バリアフリーの意味や考え方をおさらいし、その問題点と課題、心のバリアフリーについて触れていきます。

バリアフリーとは?
内閣府の調査によると、私たち日本人のほとんどは「バリアフリー」という言葉を知っているようです。しかし、設備面のバリアフリーという言葉が浸透している反面、そのほかのバリアフリーについては認識が薄い様子。この章では、「そもそもバリアフリーとは何か」について整理してみます。
バリアフリーという言葉の意味
バリアフリーという言葉は、直訳すれば「障壁の除去」という意味ですが、辞書では「高齢者や障害者が社会生活を送るうえで障壁となるものを取り除くこと」(引用:大辞林)とされています。
まず「バリアフリー」と聞いて、車椅子用のスロープや、手すりなどの設備を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。以前は、このような物理的な障害を緩和することを指していましたが、現在では社会制度や人々の意識を含む、あらゆる障壁を取り除くことを指すようになりました。
この「あらゆる障害(バリア)」について、一般的に「物理的なバリア」「制度的なバリア」「文化・情報面でのバリア」「意識上のバリア」の4つのバリアがあるとされています。
そして、バリアフリーと合わせて使われるようになった言葉として「ユニバーサルデザイン(Universal Design:どのような人でも使いやすいデザイン)」や、これらと意味が近い言葉として「アクセシビリティ(Accessibility:どのような人でもどのような環境においても情報やサービスにアクセスしやすいこと)」があります。
バリアフリーの定義、考え方は
バリアフリーという言葉は、時代の流れとともに人々の認識が変化していることから、明確な「定義」よりも、「考え方」という視点で捉えたほうが良いようです。内閣府が提唱しているバリアフリー推進要項で述べている、バリアフリーに対する考え方をまとめると、以下のようになります。
「人の能力や個性はひとりひとり違い、性質が全て同じという人は誰ひとりおらず、また、ひとりの人のなかでも環境や状況によってその性質は刻々と変化していくものである。そのため、障害の有無や年齢にかかわらず、ひとりひとりが自立し、お互いを尊重して社会生活を送ることができる環境を整備していくことが重要である。特に障害者・高齢者・妊婦や子供連れの人々が社会生活を送る上でバリアとなるものを取り除くとともに、新しいバリアを作らない施策(ユニバーサルデザイン)が必要である。」
参照:内閣府:バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進要項
この内容からも、バリアフリーという考え方は、「どのような人でも喜びを持って社会生活を送れる世の中にしていこう」という、とても前向きなイメージの言葉として定着してきていることがわかります。
バリアフリーに関する法律

政府はバリアフリーに関する法律を定め、バリアフリー化を加速させることに注力してきました。そして今、国民のバリアフリーへの認識の高さ・設備の改善等が結果としてあらわれています。
2006年に成立 バリアフリー新法
高齢者や障害者が気軽に移動できるよう、段差などを解消することを目指した、通称「バリアフリー新法」が2006年に成立、施行されました。
「利用者5000人以上の駅やターミナルなどのバリアフリー化100%」や、「その他公共交通機関や特定の建築物などへのバリアフリー化」などを義務付けたものです。最大のポイントは、計画段階から障害者や高齢者の意見を求めて反映させたこと。
駅からバスに乗って目的地に向かうといったルートを想定し、電車や駅、歩道、施設の内部などに至るまで、階段や段差をなくすよう検討を進めました。
現在、新しい建物には必ずと言って良いほど車椅子で利用できるトイレが設置されていたり、ノンステップバスが当たり前に見られるようになったりしているのは、この法律によって世の中のバリアフリー化が進んだ結果であると考えられます。
そして、このバリアフリー化実施への理解や協力を求める「心のバリアフリー」も国民の義務となっており、私たちの中にバリアフリーという言葉が浸透しているのは、この施策の結果とも言えそうです。
バリアフリー新法の基準は?その概要
バリアフリー新法によって、バリアフリーの基準が詳細に設定されるようになりました。
建築物に関するバリアフリー基準として、床面積2000㎡の建物には、最低限適合させる必要がある「建築物移動等円滑化基準」と、できるだけ適合させる努力をするべき「建築物移動等円滑化誘導基準」のふたつが設けられています。出入口、廊下、エレベーター、トイレなど建物内の設備に関して、「どのくらいの幅か」「数はいくつか」など細かく決まっており、チェックシートがあります。例えば、“出入口”に関する建築物移動等円滑化基準は、玄関出入口の幅を80cm以上確保することとなっています。これが建築物移動等円滑化誘導基準になると120cm以上と定められており、さらに利用者にとって優しい設定となります。
バリアフリーの問題点

これまで多くの改善が見られた国内のバリアフリーですが、利用者の視点に立てばまだまだ課題、問題点はたくさんあります。今までと同じ取り組みを重ねることで、さらなる改善は見込めるのでしょうか。
物理的と心理的 それぞれの問題点
バリアフリー新法施行以前に比べれば、現在の日本のバリアフリー化は素晴らしい成果を遂げてきました。ですが、実際の利用者目線で見れば、まだまだ不便や危険が山積みであることは否めません。
例えば、施設から施設間の移動には細かい段差などの不備が残っていたり、古い観光地では景観や伝統を守るためにバリアフリー化が難しかったり。また、小さな商店街などでは誰もが利用しやすいスペースを確保することは難しいのが現状です。これらの物理的な問題の解決には、とにかく費用がかかり、時間もかかります。
そして、たとえ物理的に改善されていたとしても、実際に利用者が使いやすいものになっているかというと、必ずしもそうだとは言いきれないものがあります。そこには周りの理解や思いやりがあってはじめて有効に使える設備もあるからです。
例えば電車の優先席に優先対象ではない人が座っていたらどうでしょう。せっかくのバリアフリーが活用されていないことになります。
こうしたことから、現在改善するべき問題点として、以下の4点が考えられます。
①「障害者などのハンデがある人の存在そのものに対する認識が薄い」
②「その人たちがどのような障害を感じているのかに対する理解が少ない」
③「①②の情報を知る機会が少ない人が多い」
④「障害者と触れ合う機会が少ないため意識できない」
つまり、私たちひとりひとりが、障害者など対象の方に対する理解を深めることが強く求められているのです。
誰もが使いやすいを目指すユニバーサルデザイン
上記のように、「今まであった障害を取り除く」という考え方だけでは、状況の改善は難しいと言えるのかもしれません。バリアフリー化と合わせて、どのような人でも利用可能なデザインである「ユニバーサルデザイン」を取り入れていくことが現代の主流となっています。
この考え方は、バリアフリーのように対象者を限定せず、「どのような人でも使いやすい」という点が特徴です。
前述の内閣府が提唱しているバリアフリー推進要項における「新しいバリアを作らない施策」がこれにあたります。はじめから様々な人が利用することを想定したデザインであれば、そもそもそこに障害がおこらないことになります。
例えば、視覚障害者用の黄色い誘導ブロックは、車椅子や杖の利用者にとっては走行や移動のしづらさの要因となってしまうこともあります。たったひとつの設備に対しても、「ある人にとってはよくても、ある人にとってはよくない」という事態が発生するのです。「誰もが使いやすく」という視点をもって世の中をデザインしていくことが必要であると言えます。
ユニバーサルデザインについては、こちらの記事も参考にしてください。
「知っておきたい あなたの身近にユニバーサルデザイン」
バリアフリー化は私たちの心の中から

旅行で伊勢志摩を訪れた障害者や高齢者をサポートするNPO団体、“伊勢志摩バリアフリーツアーセンター”では、「パーソナルバリアフリー基準」というものを開発し、活動の軸としています。
これは、「旅行者が行けるところに行く」のではなく、「旅行者が行きたいところに行くために、それぞれの状況に合わせて相談に応じる」というシステム。
例えば、伊勢神宮で実際に行われている活動として、玉砂利を力強く走行できる車椅子・ウィルの貸し出しをしたり、階段を車椅子のまま登れるようヘルパーを配置したりしています。
行きたい先が物理的にバリアフリーでなくても、本人の「行きたい」という強い気持ちや介助・補助などをプラスすることで、障害となっていたものが障害ではなくなるという考え方です。この団体には、すでに利用された方々から多くの感謝の言葉が寄せられており、取り組みの成果は高いと言えます。
まずは「自分とは違う生活をしている人も同じ社会で活動している」という認識をお互いに高めることが重要ではないでしょうか。
心のバリアフリーに着目すれば、ただ「知る」というシンプルなことだけで解決できる問題もあることがわかります。知っている人はそれをどんどんと発信し、知らない人はそれを無理なく受け取ることができる社会になっていけば、日本のバリアフリー化は今まで以上によいものになるかもしれません。
また、障害のある人に接することで、今まで見えていないバリアに気付くことができるはずです。差別や「障害」という偏見を持たずに、それぞれの違いを受け入れることが重要だと言えます。
まずは「知る」、そして「接する」「理解する」。「バリアフリー化」は私たちの心の中から始まるのです。