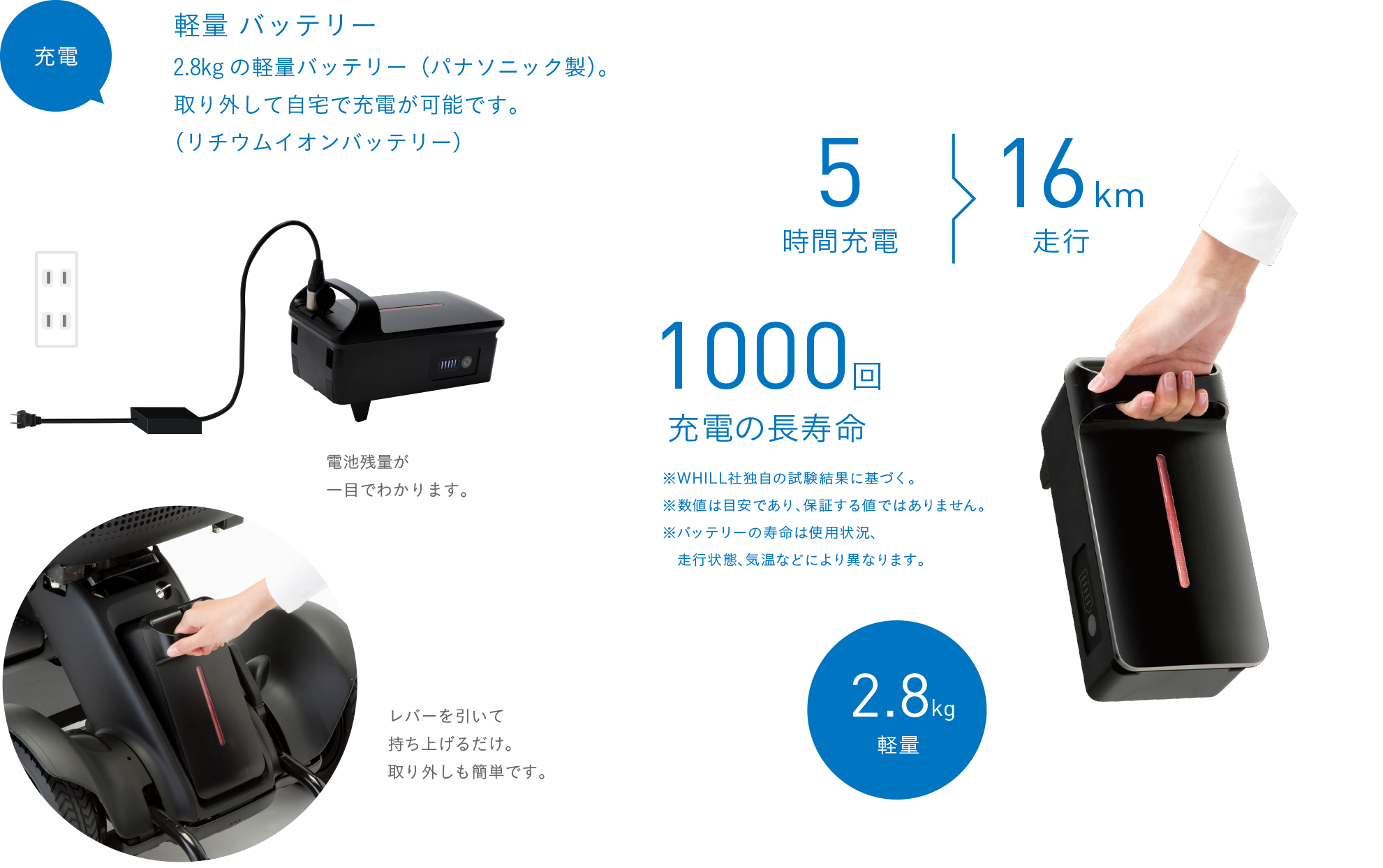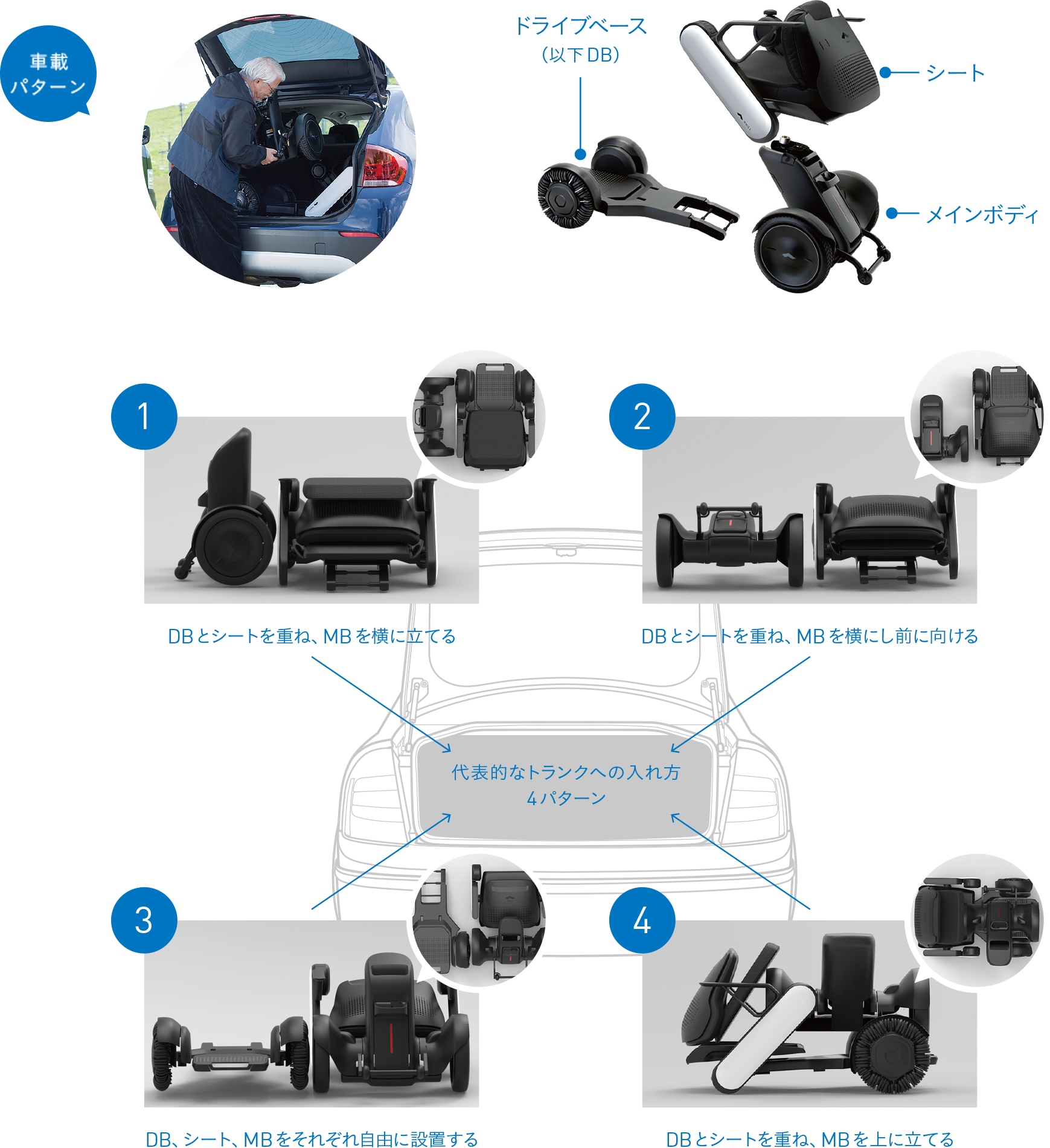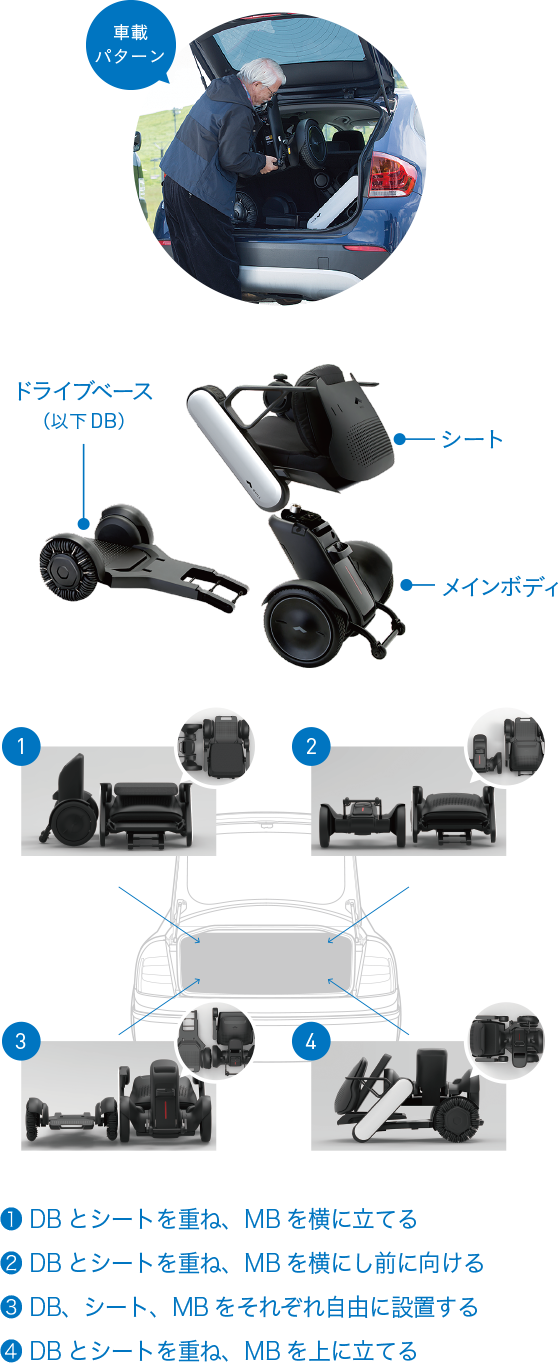車椅子利用者であっても健常者と同じように外に出て生活し公共の施設を利用している国もあれば、車椅子利用者をほとんど見かけない国もあります。それはバリアフリー化が進んでいるか・いないかに関係しているのかもしれません。そこで今回は海外のバリアフリー事情と日本の現状を比較してみたいと思います。
日本の車椅子移動、バリアフリーの現状は?

日本のバリアフリー化は、海外に比べてどの程度進んでいるのでしょうか? 日本の現状や、最近話題になったバリアフリーに関するニュース、今後の政策についてまとめました。
日本のバリアフリーレベル
日本のバリアフリーのレベルは、一概には高い・低いとは言えません。
「エレベーターが多い」「段差が少ないので移動がラク」という意見がある一方、「車椅子で入れる店が少ない」「エレベーターがない駅がある」という意見もあります。
バリアフリーの設備・施設が増えてきていることは確かですが、どこに行ってもバリアフリーになっているとはまだ言えないのが、日本の現状のようです。
制度やサービスを完備していても…意識改革の必要性
2017年に、ある車椅子利用者の、格安航空の飛行機に搭乗する際のトラブルが話題になりました。
同行者に車椅子を担いでもらいタラップを上ろうとすると、規約違反ということで制止されてしまい、仕方なく階段に腰掛け、自身の腕の力で一段一段タラップを上がって搭乗することになったというニュース内容です。
この出来事が公になり、航空会社に対するバッシング、SNSなどで炎上する騒動に発展しましたが、利用者側が航空会社に対して、事前申告をしていなかったことが判明すると、またその利用者もバッシングを受けることになってしまいました。
当時この騒動は論争を巻き起こしましたが、そもそもの問題は何でしょうか?
どちらが是か非かということだけではなく、制度として車椅子利用者は飛行機に搭乗できるものの、事前申請が必須であること、自力で搭乗することを条件とされたことに対し、利用者がタラップを腕の力で搭乗しようとしたことに対して、屈辱的だと必要以上の騒ぎになったこと。
これらは日本のバリアフリー制度、バリアフリーへの意識に、まだ課題があることを象徴するできごとかもしれません。
日本の法制度と海外事情
昭和45年に施行された日本の障害者基本法は、これまでに何度か改正されていますが、障害者が障害者ではない人と同等の生活が保障され、自立と社会参加の支援が定められています。
また公共の施設・情報利用に関するバリアフリー化も義務づけられました。
一方で、海外でも障害者に関する法律がそれぞれの国で定められているようです。いくつかの国の法律をピックアップしてご紹介します。
アメリカ ADA 障害を持つアメリカ人法

アメリカでは1990年にADA(= Americans with Disabilities Act 障害を持つアメリカ人法)が施行され、障害者に対する差別と障害者を排除するような基準を設定することが禁止されました。
この法律により雇用・公的機関・公共施設などでの障害を理由とした差別が禁止され、平等が保障されています。日本との違いは、雇用に関しては障害者を雇用するように義務づけられてはいないことです。
また日本では罰則やペナルティがないのに対し、アメリカではADAに違反した人に対しては罰則があることも異なる点です。
ドイツ 障害者平等法

ドイツでは2002年に「障害者平等法」が施行され、2016年に改正されました。その時の改正では、施設の新築・改築・増築の際にはバリアフリー化を義務づけました。またバリアフリー化された施設のみが賃貸可能となりました。
フランス 障害のある人々の権利と機会の平等、参加および市民権に関する法律

フランスでは2005年に「障害のある人々の権利と機会の平等、参加および市民権に関する法律」が施行されました。この法律により新築の際には政令に従いアクセシビリティ(バリアフリー)を確保することが義務づけられました。
しかし既存の建築物に関しては、遺産保護のために改修に制約が生じる場合は適用除外となることもあります。古い歴史的建物は今後も障害者にとっては利用しづらいかもしれません。
展開される様々なサービスと利用者ならではの情報共有
法制度だけでなく、先進的に様々なサービスを展開している国もあります。
香港での障害者の移動

香港では障害者がスムーズに移動できるサービスが整えられつつあります。
例えば車椅子のまま乗車可能なタクシーや、車椅子スペースがあるフェリーなどがあります。
また「リハバス」と言って、障害者が通勤・通学などをする際に特別交通サービスが提供されています。
さらに高齢者を乗せるイージーアクセス・バスなど、障害者・高齢者への特別支援が実施されています。しかしまだ障害者の移動手段は不足しているため、全ての人が不自由なく移動できるようすることが今後の課題です。
イギリスのバリアフリーガイドサイト

イギリスでは「グッドアクセスガイド」というwebサービスがあり、国内の行きたい地域や受けたいサービスを検索ボックスに入れると、条件に合う施設を調べることができます。
例えばバリアフリーのトイレがあるホテルを探したいときに、地名と“ホテル”を選択し次のページで“バリアフリートイレ”をクリックすると、対応した宿泊施設が検索できます。
個人による積極的な情報共有も
国や企業による制度やサービスの提供をただ待つだけではなく、車椅子の利用者自身が、同じ障害を持つ人同士でコミュニティを作り、各国のバリアフリー情報の交換をしたり、ブログやサイトを立ち上げたりしています。
日本に向けては、電動車椅子を利用している Josh Grisdaleという方が「アクセシブルジャパン」というサイトを立ち上げています。「Accessible Japan’s Tokyo」という書籍としても発売されており、利用者ならではの視点での東京の観光地のバリアフリー情報などが掲載されています。
電動車椅子での移動事情

電動車椅子で公共の施設を利用するのにどのようなルールがあるのでしょうか?
電動車椅子で鉄道を利用する際、アメリカ・イギリス・オーストラリア・スウェーデンなどでは車椅子のサイズに制限があるようです。鉄道によっては、ISOに基づき全長 1,200mm 、全幅 700mm 以下のサイズが設定されていることもあります。また回転するのに必要な面積の制限を設けている鉄道もあります。
電動車椅子の操作方法にはハンドル型(シニアカー)・スティック型とありますが、これらの国々ではどちらのタイプでもサイズ内であれば利用できます。しかしイギリス・フランス・ベルギーを結ぶユーロスターは、ハンドル型を利用する際には48時間前までに事前申告が必要です。鉄道によって細かなルールが決められていることもありますので利用する前に確認することをおすすめします。
日本では2018年4月からハンドル型電動車椅子利用に関する基準を大幅に緩和し、サイズと小回りが基準対象となりました。
2020年に向けて
2017年2月、政府は2020年に向けて、「ユニバーサルデザイン2020行動計画」を発表しました。
主な取り組みは、「心のバリアフリー」と「ユニバーサルデザインの街づくり」です。
心のバリアフリーでは、学校、企業、地域などさまざまなところでバリアフリーの教育・研修を進め、国民全体のバリアフリーへの意識を高めていきます。
ユニバーサルデザインの街づくりでは、主要ターミナルと全国の観光地のバリアフリーを推進していきます。例えば鉄道駅では、大型エレベーターやホームドアの設置を進めていくことなどがあげられます。
障害の有無にかかわらず、すべての人々が助け合い、共に生きていく社会の実現、ひいては人々の生活や心において「障害者」という区切りがなくなること目指すために、社会に暮らす一人ひとりができることから始めていきましょう。
バリアフリーについては、詳しくはこちらの記事を参照してください。
「今こそバリアフリーをおさらい 意味、定義、種類、問題点について」
ユニバーサルデザインについては、詳しくはこちらの記事を参照してください。
「知っておきたい あなたの身近にユニバーサルデザイン」